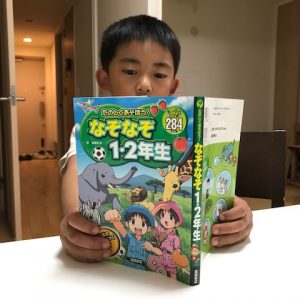自宅でもできる子どもの運動の苦手をなくす方法

- show0range
消しゴムはんこをひたすら彫り進める小学校教師(11年目)です( ̄∀ ̄)これまで56446256556年を担任。子育ての際に「どうしたらいいんだろう?」というよく教育現場で耳にする疑問を中心にお答えします。
「うちの子は私に似て運動神経が悪いから、体育は諦めています。」
「〇〇くんは運動神経がいいから、羨ましい!」とてもよく聞く言葉です。
うちの子は運動が苦手…と諦めている方もいるかもしれませんが、私は小学生の運動能力については「経験値の差」でしかないと考えています。
もちろん体を動かすのが得意で「突出した才能」の持ち主こそ現れますが、経験させておくべきことさえしておけば小学校の体育の中で取り組む内容では「突出してできない子」はなくせると考えています。
この記事では、運動の種類別に「経験させておくべきこと」「家でもできる運動」をご紹介することで、小学校の体育の授業や休み時間での遊びの中で、最低限必要な力をお子さんにつけてもらい、「体育は苦手です。」の声を少しでも減らせるよなお話をさせていただこうと思います。
私はスポーツ学を専攻していたわけではないので専門的なところまではつっこんでお伝えすることはできませんが、教師として子ども達と向き合ってきた経験からわかること、考えられることをお話ししたいと思います。
走ることの苦手を克服する方法
走ることに対して苦手意識を持っている子どもは学級に半数程度、またはそれ以上いると思います。
私自身も走るのが大嫌いでした。(今もですが、、笑)
走るのが苦手な子は足首が硬いことが多い
走るのが苦手な子ども達をみて気づいたのは「足首がかたい子が多い」ということです。実際私自身も足首が太く、稼動域が人より少ないことで足が遅かったのだなと、今さら気づきました。。
例えばブーツやハイカットのシューズを履いて走るのは困難ですよね?足をどれだけ早く動かしても、足首がかたいと推進力が半減するのだと思います。
走るフォームや歩幅など、他にも多くの要因が考えられるかと思いますが、まずは足首の柔軟性を高めることが、苦手意識克服の第一歩であると考えます。
実際、小学校にはストレッチの経験がないという子どもは多いように感じます。体の柔らかい幼少期から稼働域をフルに使っておくことはとても大切だと思います。
走ることの苦手をなくすために家庭で経験しておいた方がいいこと
- 足首、股関節のストレッチ
- 鬼ごっこ等の遊びながら走る習慣作り
- 大人との散歩で歩幅を広げる。(買い物も歩ける距離なら歩きましょう。)
投げることの苦手を克服する方法
私がこの記事を書くきっかけになったことがあります。
5年生の長身の女子児童だったのですが、走るのはそこそこ速く、マット運動等も普通にできる子どもでしたが、ボールを投げることができなかったのです。
お母さんに話を聞くと「そういえば、ボールを投げるというタイプの遊びはさせたことがない」とのことでした。
ボールを投げるという運動だけ突出してできないというのは珍しい例ですが、やはり「投げる」という運動も経験しておく必要があると強く感じました。
投げるのが苦手な場合は遊びながら肩の柔軟性をあげ手首の使い方を教えてあげる

「投げる」という運動の中心となるのは肩と手首の使い方です。
走ること同様、肩の柔軟性、稼働域を増やすということと手首を鍛えることが大切になると思います。
そして、「投げる」遊びを家でもやることは大切です。
軽くて柔らかいボールを箱の中に投げ入れてみる。
ボールでなくてもティッシュを丸めたものをゴミ箱に入れる遊び等、親子で楽しめる競技をやってみてもいいと思います。(家庭で許される範囲で笑)
様々な物で投げる遊びをして使い方を考えるきっかけを与える
もう1つポイントとして様々なものを投げさせるということも大切です。
「ティッシュは軽くて狙いにくい、強く投げなければいけない」
「このボールはちょうどいい重さだ」
等、考えさせることで手首の使い方が上手くなっていきます。
サッカーはなぜサッカーボールなのか?バスケットボールは?野球ボールは?全て適した質量と形、大きさであることがわかります。
様々な球技に対応できるように色々なボールで、色々な狙いで遊べるとよいと思います。
投げることの苦手をなくすために家庭で経験しておいた方がいいこと
- ボールを投げて的に当てたり、箱に入れる遊びで親子で競う。
- 手首、肩のストレッチ
- キャッチボール(様々なボールでやるとさらに効果的)
ボールを受けることの苦手を克服する方法
ドッジボールやキックベースで飛んできたボールをキャッチできない子どもは本当に多く、高学年でもボールを受けることが苦手な子は3割から5割程度はいるのではないかと思います。
野球の打球のように速い球をグローブでキャッチするような高い技術は小学校では求められませんが、せめてドッチボールでキャッチできるようにはなってほしいものですよね。
ボールを受けるのが苦手な根本原因は反応の遅さ
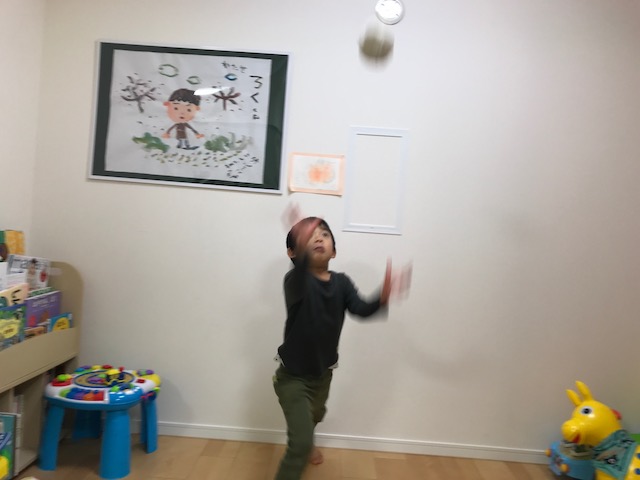
ボールをキャッチできない原因として考えられるのが
- ボールが飛んできたら目をつぶってしまう
- ボールに合ったキャッチの手の形がわからない
の2点に加え、「反応の遅さ」があげられると思います。
「反応の遅さ」は経験を積み重ねることで身体が合ってくるようになるので、その競技を繰り返すしかありません。最初の2点は家でもなんとかできると私は考えます。
ボールへの恐怖心はボールをよくみる練習を
「目をつぶってしまう」ことの原因は恐怖心に他なりません。
こちらも経験を積み重ねることで払拭されるものではありますが、キャッチするためにはボールをよく見る訓練が必要だと思います。
家でも出来そうな遊びとしては下記のようなものがあります。
- カラーボールのような軽くて安全なボールを用意
- 大きくシールを貼ったり文字やマークを描く
- 親がフワッと投げ、子どもキャッチするまでに何が描かれているかを答える
カラーボールは100円均一でも複数個手に入るかと思いますので、例えば10までの数字を大きく書き込んでおき、「どれを投げるかわからないよ」という形をとるのもよいでしょう。
男の子はとくに相当燃えると思います(笑)
ボールを受ける手の形は様々な物をキャッチして慣れる
もう一つ「手の形がわからない」は、【投げる】と同様なのですが、色々な大きさや硬さ、またボールでなくてもいいかも知れません、様々なものをキャッチする経験が必要です。
小さいボールを受ける時と、大きいボールを受ける時の違いは教えても身につきません。
遊びの中で経験不足を補えるように工夫してみるとよいと思います。
ボールを受けることの苦手をなくすために家庭で経験しておいた方がいいこと
- ボールをよく見る遊び
- 様々な形のボールやものをキャッチする遊び
バランスをとる(体幹を鍛える)ことの苦手を克服する方法
マット運動や跳び箱などの運動をする上で、最も大切なのは自分の体を思っているように動かすということです。
バランス感覚を確認しながら調整する
立った状態で目を閉じて「前へならえ」をしてみてください。
目を開けてみると、意外と左右の手の高さが違ったり腕が地面と平行になってなかったりします。
これは頭で考えていることと実際の動きに誤差があるということです。
片足立ちも目を瞑ると難易度が跳ね上がりますよね。
実際に目をつぶりながらマット運動や跳び箱などをさせることは絶対にありませんが、自分の体が今どうなっているのかを理解し修正できる能力が高まれば、バランス感覚が研ぎ澄まされ、様々な運動に役立つ「体幹」を鍛えることができるのです。
バランスをとることの苦手をなくすために家庭で経験しておいた方がいいこと

家で簡単にできる遊びとしては、積み上げてグラグラする座布団に正座する遊びはいかがでしょう。私も息子にさせましたが、とても喜んでやっていました。
不安定なものの上に乗る遊びは、安全面は気を使わなければなりませんが、大変効果が高いと思います。
平均台のように綱渡り風の遊びをさせるのも同様に大切な経験だと思います。(平均台は保育所や幼稚園でもあると思いますが。)家のものでできる「バランスゲーム」ぜひ考えてみてください。
- グラグラ座布団
- 綱渡り風のゲーム
- 新聞や座布団を島に見立てて、ソファーにたどりつく跳び石風ゲーム
まとめ
他にも様々な「苦手」が考えられますが、やろうと思えばすべて遊びの中で経験させられるというのが私の考えです。
自転車の補助輪がなかなかとれない子どもが近ごろ減ってきていることはご存知でしょうか。
これは間違いなく「ストライダー」の功績だと思います。自分の足で歩き漕ぐ遊具ですね。
私の息子もストライダーで遊んでいたおかげで、5歳の誕生日に買ってもらった自転車には補助輪なしですぐに乗れるようになりました。
どんな「苦手」も、その前身となる運動を経験させておくことで解決できるといういい例です。
私は今回のお話を通じて、もう一つテーマを持っていました。それはお子さんとのコミュニケーション不足の解消です。
今回挙げさせていただいた遊びの例はすべて、子どもだけではできないことです。
パパママとの遊びを通して培った経験値は、他の何物にも変えがたい最高の体験であり、何よりもの自信につながるのです。
今回のお話を機にたった一度でもお子さんとのコミュニケーションの時間を創り出せたなら、大変嬉しく思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。